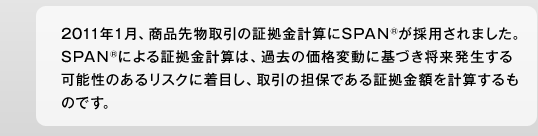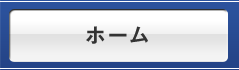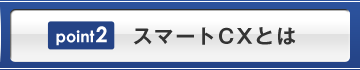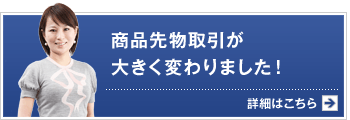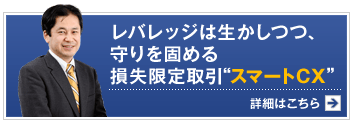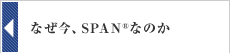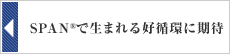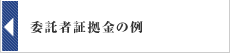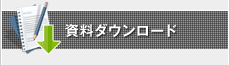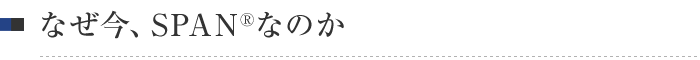

[深野]SPAN®とは価格変動リスク対応型の証拠金計算システムのことです。やや教科書的な説明になりますが、商品先物取引で、保有する建玉のリスクが高まっている場合には証拠金の額を多めに、反対にポートフォリオ全体でリスクが小さい場合には証拠金の額を少なめに徴収するシステムということです。その際、リスクが高いのか低いのかを評価・判断する基準として過去の値動きを参考にします。そもそも証拠金は取引の担保ですが、例えば東京工業品取引所の金(標準)先物を1枚取引するのに、いったいいくらの証拠金を預ければいいのかという話です。10万円なのか20万円なのか、それとも5万円でいいのか。5万円ならたくさんの取引(建玉)ができるけれど、20万円なら取引(建玉)が少なくなります。
投資家にとっては、投資効率の観点からいえば証拠金は少ない方がいい。しかし商品先物取引業者にとってみれば、少額の担保では相場の急変時に担保不足に陥る危険があります。そして、いま“相場の急変時”といいましたが、裏を返せば、相場が急変しなければ担保不足に陥る可能性は低くなりますよね。つまり証拠金の多い少ないは、相場変動が建玉にもたらすリスクを勘案して決めるのが合理的だということになります。では現在の相場の変動率が高まっているのか、それとも小さくなっているのか、そしてそれをどうやって知るのか。その手掛かりは過去の値動きにあります。これがリスク対応型の証拠金計算システムの根本的な考え方なのです。
[深田]SPAN®はリスクの大小に証拠金の額を相関させていくものですから、非常に理にかなった美しいシステムです。そして改めて説明を受けると、やはりその合理性に納得させられます。私が特にSPAN®が優れていると思うのは、価格変動リスクや取引(建玉)状況のリスクが高い時には厚めの証拠金、そうでない時は少なめの証拠金という点です。先ほど投資効率のご指摘がありましたが、例えばあるとき100万円の投資資金を用意し、値上がりの期待できる商品を買おうとしていて、20枚の買い取引(建玉)をしたら証拠金が100万円必要だったとしますよね。もちろん私はそういうポジションの取り方はしません。せいぜいその何分の1の証拠金額となるよう、自分が受け入れられるリスクの量をコントロールするわけですが、仮に証拠金を20万円以内に抑えたいなら、最大でもこの状況では4枚までしか取引(建玉)しないとか、限月間や商品間のスプレッド取引をしたりするわけです。ということは、証拠金それ自体が投資リスクをコントロールしてくれることになります。
[深野]おっしゃるとおり。相場が動いている時に積極的にリターンを獲りに行くというやり方もあるでしょう。しかしリスクに敏感であることは、リターンを獲る以上に重要だと思います。
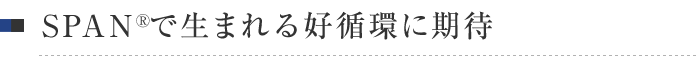

[深田]SPAN®は世界の金融市場、国内の証券・金融市場ですでに広く使われています。すなわち多くの投資家やトレーダーをはじめとする金融関係者の間では“国際標準”的な位置づけを獲得しているのですよね。
[深野]そう。いまや世界最大の先物取引所となったシカゴ・マーカンタイル取引所がSPAN®を開発したのは1988年のこと。さまざまな取引(建玉)で構成するポートフォリオ総体のリスクを評価しフェアな必要証拠金額を算出するSPAN®は急速に世界の金融市場に浸透していきました。実は、世界ではSPAN®とは異なる証拠金システムを採用している取引所もありますが、リスクベースで証拠金を計算するという根っこの部分はいっしょなんですね(笑)。
[深田]ですから日本の商品先物市場でもSPAN®が始まったことで世界の市場とインフラを共有することになり、世界のトレーダーも利用しやすくなるのではないでしょうか。そして市場参加が増えれば市場流動性が増大し売買注文はより約定しやすくなりますから、今度はリスクヘッジを目的としたヘッジャーも入ってくる。するとさらに流動性は高くなって、またトレーダーにとっての魅力が増すという好循環が生まれますね。
[深野]ええ。そうなれば、いま日本国政府が議論している“アジアのメインマーケット”にも近づきます。ぜひ、そういう夢を持って臨みたいですね。
[深田]私も、SPAN®の導入に対してはポジティブに考えています。たとえば私はオプション取引もやっているのですが、こうした国内の証券・金融のデリバティブ取引では既にSPAN®が導入されています。商品先物取引のオプションはいま現在は低調ですが、オプション取引を上手く利用すればリスクもコントロールできるので、SPAN®の導入により活性化することが期待できます。そうなればSPAN®のメリットが最大限享受できるのでありがたいですよね。本来、投資は自己責任で、リスク管理は投資家自身がするべきものだと思いますが、なかなかそれができない投資家も多いものです。そういった投資ビギナーにとっては、商品先物取引がぐっと身近になりそうですね。
[深野]同感です。これまで以上に国内外、業界の内外の投資家が商品先物取引市場に注目し、市場参加者の厚みが増していきそうです。市場参加者が増えれば増えるほど流動性もさらに高まっていきますから、業界の健全な発展に寄与していくものと見ています。

[深田]では実際の運用はどのようになるのでしょうか。
[深野]投資家が商品先物取引業者に預託する証拠金のベースを計算するのは㈱日本商品清算機構(JCCH)です。JCCHは一般的に“クリアリングハウス”と呼ばれる清算機関で、買い手に対しては売り手、売り手に対しては買い手となります。多くの人は投資家同士が売ったり買ったりしていると思っているかも知れませんが、実は違います。JCCHが間に入ることによって、万一、売買当事者の一方が買いなり売りの契約を履行しなくても相手方に迷惑がかかるのを防いでいるのです。
[深田]デフォルト・リスクの回避役ということですね。それに商品先物取引業者が投資家から預かった投資資金はすべて、JCCHの口座で管理しなくてはならないルールになっているから、本当に万一、その商品先物取引業者の経営が危うくなったとしても、投資家の資金は守られるんですよね。
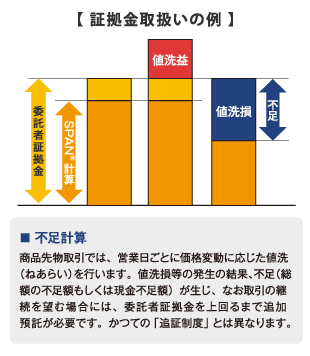
[深野]その通り。そしてそのJCCHは商品の過去の値動きからリスクを割り出し、証拠金のベースとなるSPANパラメータと呼ばれる変数を計算し、商品先物取引業者に提示します。その変数にはプライス・スキャンレンジ(PSR)と呼ばれるものが含まれますが、これら変数を用いて証拠金を計算します。その計算結果はいわばリスクをコントロールするための最低水準の額なので、これに一定の割合を乗じて投資家に知らせるやり方が多いかも知れません。一番シンプルな例でいえば、例えば他の変数を考慮せずPSRのみで計算する場合、PSRが10万円、乗じる割合が100%なら10万円のまま、割合が110%なら11万円、120%なら12万円ということになりますが、こうして計算結果に一定の割増しを加えたものを“委託者証拠金”と呼びます。
[深田]つまり委託者証拠金は商品先物取引業者によって異なる。
[深野]そう。そして投資家は常に自分の取引口座には委託者証拠金以上の金額をキープしておかなくてはなりません。ですから極端な例でいえば、12万円で1枚の取引をすることは可能ではあるけれど、それだとちょっとでも相場が不利な方向に動いたら証拠金を足さなければならなくなってしまう。それでは投資家だけでなく証拠金を管理する商品先物取引業者も大変ですから、現実的には「いくら以上の金額を常に維持しておいてください」というやり方をする場合もあるでしょうね。つまり実際の運用は商品先物取引業者によってことなるということです。